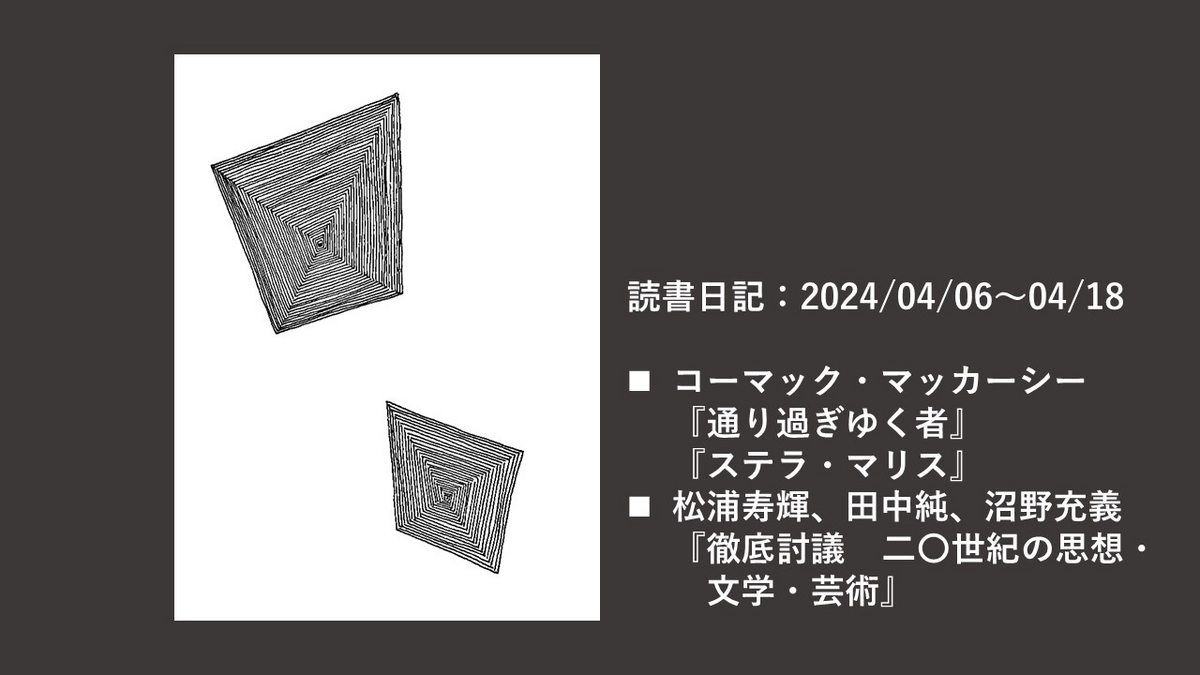
コーマック・マッカーシー『通り過ぎゆく者』『ステラ・マリス』
キャンバスのバッグをとって台所に入り缶詰とコーヒーと紅茶を入れる。皿などの食器や台所用具も少し。ダッフルバッグに本を詰めキャンバスのバッグといっしょにこれまたドア口に置く。小型のステレオ装置とカセットテープの入った箱も。電話のジャックを壁から抜きベッドからカバーと枕をとって最後にもう一回り室内を歩く。猫のトイレをとりあげる。所有物は多くないのにすでにあまりにも多すぎるように思えた。コードをコンセントから抜いて電気スタンドをドア口まで持ってきたあと荷物を全部運び出してトラックの運転台に積んだりクレーンの前の隙間に突っ込んだりしはじめた。作業は五往復で終了。それから膝をつき猫に話しかけながらベッドの下に手を伸ばすとやがて猫に手が届いた。おいで、ビリー・レイ。なんでも永遠には続かないんだよ。
――『通り過ぎゆく者』
世界には喜びが少ししかないということは単なる物の見方の問題じゃない。どんな善意も疑わしいの。あなたが最後に悟るのは世界はあなたのことなんか考えてないってこと。考えたことがないってことよ。
――『ステラ・マリス』
コインの裏表のようになった姉妹篇。それぞれ兄と妹を主役にしているから兄妹篇か。どちらが先どちらが主と云うこともなく一方だけではよくわからないようになっている。もっとも2冊とも読んだところでよくわからないのだけれども……。何かの陰謀に巻きこまれたかのように追いつめられてゆくと云う漠然とした筋立て以外にプロットらしいプロットのないまま曠野をさまようみたいにしてさまざまな光景と出会っていろいろな人びとと言葉を交わしときにはひとりで黙考にふける『通り過ぎゆく者』、脱線や切断をくり返す対話その成立しえない言葉のやり取りのなかで記憶と思索が断片的に語られてゆく『ステラ・マリス』。訳者の黒原敏行は『通り過ぎゆく者』から読むことを前提に語っていて本国での刊行順もその通りであるし分量から云っても後者は前者の補足ないし種明かしのように読める。一方で山形浩生は月報でむしろ『ステラ・マリス』からのほうが読みやすいと語っていて確かにこちらを踏まえないと『通り過ぎゆく者』はだいぶわけわからん小説に思えるだろう。先ほどはこちらを補足と云ったが世界について思索を巡らせる『ステラ・マリス』のほうが短くも2部作の芯であると云うこともできる。とは云え『通り過ぎゆく者』を読んでいなければ『ステラ・マリス』はよく知らない人のよくわからない話を延々と追いかける羽目になってこれはこれで読みにくいところがあるだろう。静謐な作品ではあるが悪く云えば何も起こらないのでこれはこれでよくわからない。と云うわけでぼくは読むなら両者を並列させて行き来することをおすすめする。一方の息苦しさに耐えかねれば空気を入れ換えるようにもう一方へ逃げこめば良い。そうして行ったり来たりするうちに互いが互いの裏表になって一体となる。そうして辿り着くラストシーンとりわけ『ステラ・マリス』の結末の厳粛な祈り……。行動だけならばなんでもないようであるのに切実で哀しいものが籠められたその言葉にこちらもまた祈るような気持ちになる。そうしてわたしたちは終わりを迎える。おいで、ビリー・レイ。なんでも永遠には続かないんだよ。
松浦寿輝、田中純、沼野充義『徹底討議 二〇世紀の思想・文学・芸術』
[松浦]人類文明の突端にわれわれは今立っていて、いろんなものが煮詰まってきているんだけど、その煮詰まった挙げ句にどういう場所に出ることになるかは、皆目見当がつかない。そういう五里霧中のさなかに身を置きつつ、われわれはとりあえず目を過去に向け、二〇世紀とは何かというやや大袈裟な問いをめぐって語り合ってきたわけです。二〇世紀――それはともかく人類が多くのことを夢見た世紀でした。そのなかには十全に実現された夢もあり、されなかった夢もある。「夏草や兵どもが夢の跡」という芭蕉の句があるけれど、われわれの討議はいわば、二〇世紀の「夢の跡」を――この世紀が夢見たあまたの実現されたもの、あまたの実現されなかったものの「跡」を経巡ってゆく長い旅だったのかもしれません。
『群像』で連載されていた鼎談をまとめたもの。「二〇世紀とは何か」と云うのはぼくにとっても重要な問いで、学部生時代には一度、京都大学文学研究科の二十世紀学専修(現メディア文化学専修)に文転しようか本気で悩んでいたくらいだし、昨年書いた中篇「グラモフォンとフィルム、タイプライターのための殺人」の構想メモには「二〇世紀のダイイング・メッセージ」なる文言が残っている。なんやそれ。まあ結局中篇は別に「二〇世紀とは何か」を論じたものにはならなかったけれど、被害者のアマチュア研究者が遺した手紙として、こんな文章は書いた。彼は死の直前に、自らの死を知らないはずなのに、まるで予感しているかのようにして、愛する人に書き遺す。
あとに残るのは言葉。ただ言葉だけだ。われわれは言葉の外に出ることはできない。音楽がドレミの外では何も演奏できないように。映像が光の外では何も映すことができないように。すべてはこのどうしようもない窮屈さのなかで一切が遅れてゆく。そこには本当も嘘もない。ただ抜け殻になった死体が転がっている。コーパス。死体。全集。言葉の集積。
まだわたしの話を聴いてくれているかい?
これはぼく自身の考えていることとぴったり一致するわけではないけれども(小説のいち登場人物の手紙なのだから)、ここで語られているような、外が失われていることの息苦しさ、そこで遺される言葉の廃墟のイメージは、鼎談で語られているイメージと決して遠くないような気がする。これはぼくが優秀だと云うよりも、二〇世紀を考えるにあたって誰しもが辿り着く場所として、夢の跡、あるいは傷痕としての廃墟があるのだろうと思う。第一回「世紀の開幕」で、松浦は田中とベンヤミンを語りながら《一九世紀のパサージュに対応する二〇世紀的な特権空間というのは、ひょっとしたらアウシュヴィッツの収容所跡などがそれに当たるかもしれない》と見当を付ける。戦争。大量死。テクノロジー。血腥く悲劇的であるのにどうしようもなく惹かれるこの二〇世紀と云うテーマは、なるほど廃墟に惹かれることと近いのだろう。長い討議の終わりで、松浦はまたこの廃墟に還ってくる。ニコラウス・ゲイハルターの映画を引きながら、《二〇世紀の夢の廃墟を、どこからともなく湧いて出た霧が呆気なく呑みこんでいき、後にはただ真っ白な画面が残るだけ――というこの映像が、十二回にわたったわれわれの討議の、いちばん最後に置かれるイメージにふさわしいんじゃないかな》、と。
*
けれども一方で、果たして夢を見ているのは誰だろうかと云う疑問がないでもない。最後に儚くも恍惚としたイメージへと回収されて、鼎談自体が煙に巻かれた、もとい、霧に呑まれたような気もする。二〇世紀を語り尽くそうと云うそもそもが無茶な企てを成立させるにあたって、霧がいたるところに立ちこめていると云うか、結局のところここで語られる二〇世紀それ自体が、小部屋――その部屋の名前は「東大」だろう――に籠もった三人の夢想であるように思われてならない。三人が互いに補助線を引き合って全体を延ばしてゆく、まるで三つ編みのような構成は読みやすくもわかりやすくもありしなやかでもあり、同時に、思っていたよりも広がりがないとも云えるだろう。だからこそ、議論としては散漫になりつつも、個人的な経験、生きて積み重ねてきた記憶に基づいた後半の回のほうが面白く読めた。そもそも会話の面白さとは、そのように発散的なところ、即興的なやり取りにあるのではないか。実際本書では、各々の知識に基づく整理は勉強になりつつも、ふと思いついたように語られる素描のほうが、遙かに興味深いと感じる。
*
追記。流石にフェミニズムの章がないのはどうなの? 一応言及されていないわけではないものの、各回で断片的に扱われる程度。まあ、三人の専門の関係上、どうしてもヨーロッパ中心的にならざるを得ないところがあり、フェミニズムも同様、専門外だから迂闊な言及を避けているのだろう。
けれどもだとすれば、そもそもメンバー選定が、二〇世紀を論じるにあたってどこまで適切であったか、と云う話にもなる。とりあえず本書は、この三人で二〇世紀を語ってみたらこうなった、と云う本として読むべきなのだろう。


