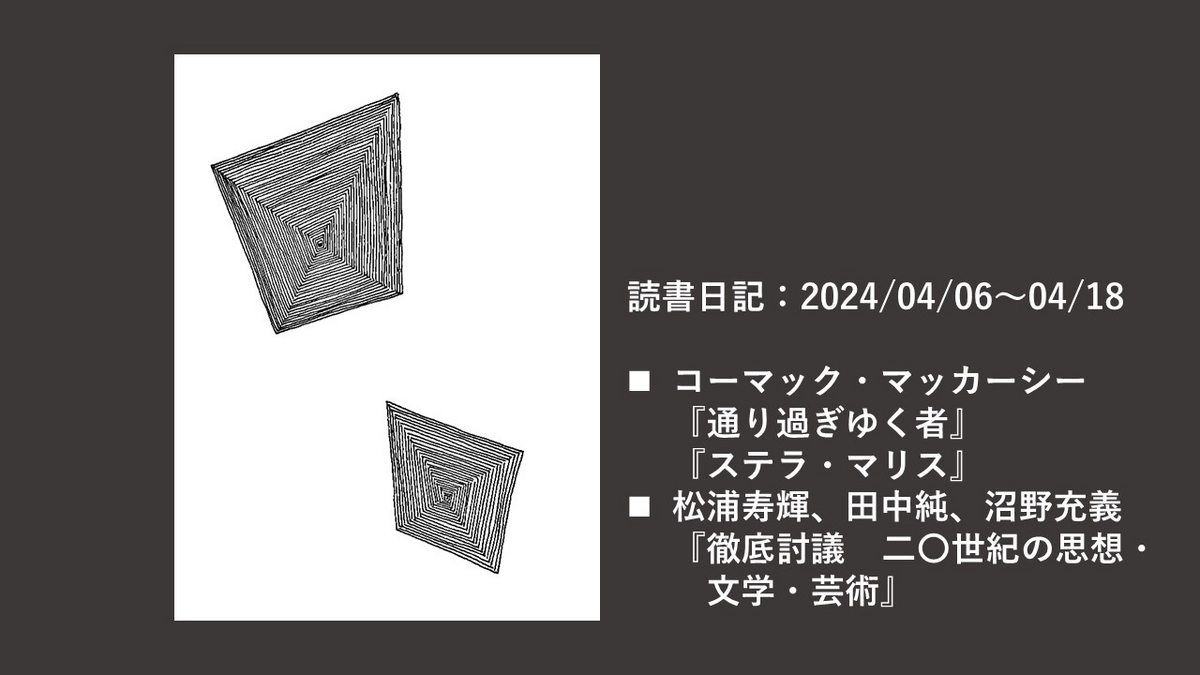国内ミステリ三冊。『禁じられたジュリエット』の感想については核心的なネタバラシを避けるものの、相当内容に踏みこんでいるので未読の方はご注意を。
北山猛邦『天の川の舟乗り:名探偵音野順の事件簿』(創元推理文庫)
心を閉ざせば嫌なことを見ずにすむが、他人の優しさに触れることもできない。
先日、連鎖と転用についてエッセイを書いた。そこでは北山猛邦の『オルゴーリェンヌ』を引き合いに出したが、あそこまで重くなくとも、と云うか、あえて軽くすることによって、本書はトリックの連鎖と転用を書いているように思う。事物の意外な連鎖が事件を起こしてしまう不思議。事物が思いがけない転用を遂げる驚き。この点で、中篇サイズで力の入った表題作よりもその続篇「マッシー再び」が印象に残る。これとこれでこんな使い方ができる――想像が転用をもたらし、創造を生む。まるで子どもの工作のような楽しさと、けれどもそれが人死にをもたらしている歪み。そこに“名探偵”の話も加わって、ずいぶんと重たくなりそうなところ、語り手の飄々として楽観的なスタイルとデフォルメされたキャラクターたち――まるで大きなぬいぐるみのようだ――によって、いっそ過剰なまでの軽さを維持している。と、云うよりも、吹けば飛ぶようなこの軽さのなかに、不意に鋭い歪みが重みとかたちを与えているのかもしれない。
正直、この軽さを生みだす何よりの根源としてこのシリーズでもっとも特異な存在は、(音野兄弟以上に)語り手の白瀬ではないだろうか?
「われわれ凡愚の人間は、精神的には始終、人殺しをしているようなものなんです」
読書会の課題本。昨年『ゲゲゲの謎』のヒットなんかもあり、横溝をいま、あらためて読むと面白いのではないかと思って手に取った。ゆくゆくは後期のシリーズにも手を出したいと思っている。そこで問い直したいのは、横溝のイメージと実態の乖離だ。つまり――、村、惨劇、トリック。それらは横溝の(少なくともぼくが思い浮かべる)イメージではあったが、その要諦だろうか? 何年か前『悪魔が来りて笛を吹く』を読んだ辺りから考えていたことではあるが、そろそろ、向き合いたい問いである。
たとえば本書に、トリックらしいトリックは登場しない。それでは何が問題になるかと云えば動機ないし毒殺被害者たちを結びつけるミッシング・リンクだが、それは村の因習や制度にからむと云うよりも、それをハックするような発想から来ている。そもそも八つ墓村自体、住民を縛るのはいにしえの伝説ではなく、かつて起こった悲惨な事件の記憶だ。横溝は実のところ、土着的な因習ではなく、イエや血が生みだす抽象的な図式にこそ関心を払っていたのではないか……、と云うコメントを読書会では提出した。とは云え、翻って「土着とは」「イエとは」と云う話にもなる。探偵小説の舞台となり、事件を駆動する、家と血と場所のシステム……。
もうひとつ注目したいのは、不完全な操りとでも云うべき真相だろう。あとからこじつけているのではないかと云う感じもするが、そのためにかえって、事件は超越的な犯人の計略と云うよりも、複数の意図の因果な絡み合いとして起ち上がる。『獄門島』にも『悪魔が来りて』にも覗かれるこうした操りへの関心は実にクイーン的と感じられて、そう云えば『Yの悲劇』も、家と血と操りの話だった。横溝の書く村はライツヴィルのように、どこか抽象的な場所にも見える。
とは云え、ほかにも鍾乳洞など見るべき点が多くありながら、小説全体としてあんまり強い印象を残さないのが不思議なところだ。なんと云うのか、立ち返るべき古典ではなく、さまざまなアイデアの萌芽をたくしこんでいる、そんな小説だと思った。じっさい読書会では、ここをもう少し洗練させたら良いアイデアになる――作例もある――と云う話にもなり、読ませる小説ではなく、書かせる小説なのかもしれない。
追記:これも読書会でのコメント。横溝作品にはよく復員兵が登場するが、自分で戦地に行ったわけではない横溝にとって、戦争とは戦場ではなく、戦後に還ってきた、たくさんの(顔を、寄る辺を持たない)兵士たちにこそ、象徴されるのではないだろうか。もちろんその存在が、ミステリ的な連鎖/転用の発想を刺激したと云う側面もたぶんにあるだろうけれども。
古野まほろ『禁じられたジュリエット』(講談社文庫)
「いいじゃない。それで」[…]「たとえ私達が、この世界のインクの染みだって。」
古野まほろの読み方がわかったので読んだ。と云うのもそれは、昨年末にアンソニー・ドーア『すべての見えない光』を再読したからだ。そのときの感想で、ぼくはドーアの小説にかつて感じていた欺瞞を表明し、けれどもその欺瞞こそ、小説と云うフィクションの魔術ではないかと思い直した。少し長くなるけれど、端折りながら引用しよう。
文庫化を機に再読。五年前に読んだとき、ぼくはドーアがこの小説をあまりにも美しく仕上げてしまっていることに反感を覚えた。それは当時、ぼくの文学的関心――と云うほかないが――が「声」とでも云うべきもっと生々しく切実なものに向けられていたことに起因するのだろう。[…]響き渡る固有の声、言葉にならない現実をそれでも言葉によって語り尽くそうとする豊穣で痛切な語り、ひいてはこちらを圧倒してくる交換不可能な人生の重みに較べると、ここはあまりに人工的で、美しいものしか書かれていない。貝、鳥、宝石。それらはいずれも標本箱に収められたりきらびやかに衣装を飾り立てるばかりで、海辺に棲む貝類の蠢きや、群れる鳥たちの落とす糞の雨に欠けているように思えたのだ――生きものたちの驚異とはそこにあると云うのに。[…]ドーアの小説にはまるで、切り出された宝石を自然の真なる美しさとして差し出されているような欺瞞がある。それは云わば、生きた鳥たちの生きた観察ではなく、殺して剥製にして鑑賞するような死んだ語りだ。
しかし今回あらためて読んでみて、この欺瞞は小説がなし得る魔術のひとつなのかもしれない、と思い直した。剥製もまた科学であり、惚れ惚れするような技術である。それによって可能になることもまた、ある。リョコウバトが絶滅してもオーデュボンの絵が残ったように、空襲で街が破壊されても模型の街はかつての建物を記憶するように、そうして模られたパリとサン・マロの小さな街が、マリー゠ロールを導いたように。
[…]書くこと。つくること。そうして世界と関わる方法は、一切の真実を捉え、すべての声をくまなく聴き取る以外にもあるのではないか。頭でっかちないまのぼくにはむしろ、それがひとつの模索するべき可能性に思われるのだ。
かつて古野まほろをどちらかと云えば好んで読みながら、ある時期からまるで評価できなくなった、そうでなくとも、自分のなかにうまく体系立てられなくなった理由は以上から明らかだろう。古野作品には明らかに《海辺に棲む貝類の蠢きや、群れる鳥たちの落とす糞の雨》は存在しない。あるいは、巨大健造さんに宛てた手紙でドーアと絡めて書いたような《生の意図せざる記録》すなわち、《かさぶたのように家の壁を覆うトタン板のパッチワーク。その場しのぎで即興的に張りめぐらされた軒下の配線。ちょっとした段差を登るために無造作に置かれたコンクリートブロックと、そのこぼれたふち。道路に大きくはみ出したプランターから伸びる蔦が屋根まで這いのぼっているさま。》と云うようなものは。モノトーンのセーラー服が象徴するように、古野作品においてあらゆる要素は洗練され、抽象的な図式に支配されてしまっている。その声は徹底して統制され、そこには《響き渡る固有の声、言葉にならない現実をそれでも言葉によって語り尽くそうとする豊穣で痛切な語り、ひいてはこちらを圧倒してくる交換不可能な人生の重み》がない。その支配の網をくぐり抜ける、したたかな生の技芸は失われているのだ。
けれどもしかし、ドーアがそうであったように、模型もまた模型をもって、語らしめるものがある。人間を人間でなくしてしまう、一種の人形劇でしかない探偵小説はむしろこの、人工的な模型ではないか? あるいはそれを製作することにおいて、浮かび上がる技芸があるのではないか? そしてこの単声的な、人工的な語りによって、何が語られるのだろうか? かくしてようやく、ぼくは古野まほろの小説がしょせん箱庭に過ぎないことを肯定し、自分のなかで位置づけることができたわけだ。《読み方がわかった》とはそのような意味である。だから、読むべきスタンスがわかった、と云うべきか。
とは云え。
ぼくがドーアをあらためて読んだときに高く評価したその記録・記述・記憶的な効用――《リョコウバトが絶滅してもオーデュボンの絵が残ったように、空襲で街が破壊されても模型の街はかつての建物を記憶するように、そうして模られたパリとサン・マロの小さな街が、マリー゠ロールを導いたように》――と、本書において古野まほろの造りあげた模型の目指すところは、似て非なるものに思われる。なぜか。それは本書が、どうしようもなく、書物を焼く話であるからだ。
*
舞台は、戦争(と云うか内戦?)状態にある独裁体制下のもうひとつの日本。ミステリは退廃文学として禁書にされ、その愛好者は思想犯として重罪となる――。その禁忌に触れてしまった女子高生六人は、二人の同級生を看守として、刑務所を模した更生プログラムに参加することになった。二人の教員が観客として見守るなか、演技だったはずのプログラムはエスカレートし、脚本にない出来事が発生する。そして舞台の幕が下りたとき、真の事件が……。
と云うあたりまでが前半の、いや2/3くらいまでの内容。解くべき謎の発生は後半、プログラムの劇的な展開がひと段落ついてからであり、それまでは執拗に、着々と、女子高生をサディスティックに極限状況まで追い込んでゆく展開がつづく。全体を二部構成と見るなら、拷問に近い状況下でそれでもなお少女たちの口から表明される「本格ミステリ」像の提示が前半の山場であり眼目、後半は事件の発生から急転直下、いきなり解決篇へと移る。事件の概要説明と解明が同時進行でなされるその後半は、黄金の羊毛亭の見立てを借りるなら、前半で語られた「本格ミステリ」の理念に対して、その実践に取り組んでいる。この実践自体は流石によく考えられていて、跋文で作者が述べているように本書の目論見を作者流の「本格ミステリ」観について実践のなかで語らしめることだとして読んだとき、優れた達成であると云うほかない。
とは云え問題は、それを成功せしめているのは何か、である。
答えはおそらく、ノイズの除去だ。と云うか、それを発生させる物理的側面の排除である。身体もそこに含まれるだろう。どう云うことか。
「終幕」を筆頭とするちりばめられた用語の数々に限らず、舞台演劇は古野作品において頻出のモチーフだが、強い光を当てられて観客のまなざしを一身に浴びながら、自らの声をつくりあげてゆくそれは徹底した身体制御の場であり、はっきり云えば、監獄や軍隊にも通じている身体支配のシステムである(ところで、古野作品における演劇はあまり現代演劇的ではないように思う――まあ、このへんはまるで詳しくないけれど)。もっとも、探偵小説もまたこのような支配を書いてきたのであり、そこでは抽象的な悲劇の構図が取り出される。世界最初のミステリとして、オイディプス王が挙げられる例を思い出しても良い。
こうした支配に対して『禁じられたジュリエット』は、内心の自由をもって抵抗する。権力が身体に対してどれほどの理不尽を強いたとしても、その心までは傷つけられない。決して支配できない。いや、権力はそれをも支配することを目論むが、強い心は、真っ当な知性は、2+2=4と云う論理は、決して曲げることはできない――。自由と、それを守るための手続き、そしてその手続きに必要なルールを対等な信頼をもって築き上げること。これが「本格ミステリ」の要諦であり、正義であり、ゆえに本書では「本格」が、理不尽なちからによる支配と対極に置かれる。その鮮やかな図式はいかにも感動的だ。
けれども、こうした解決は、いかにも抽象的に思われる。現実はなるほど理不尽だが、その理不尽はある一点から降り注ぐ光のような支配に基づくのではなく、もっと複雑な構造から立ちあらわれるのではないだろうか。ちょうどいま、ぼくはロバート・ダーントンによる歴史研究『検閲官のお仕事』を読んでいるが、それを冒頭少し読んだだけでもわかるように、権力による支配のシステムは、収容所において看守が行使するほどに明白ではない。それは具体的な事物――人間と書物エトセトラ――による遙かに複雑な連鎖のなかからようやく取り出されるものであり、ときとして捩れた構図をも生みながら、支配のシステムは生活のなかに埋めこまれ、生活は支配のなかに埋めこまれる。得てして社会学が実践するように、世界に対するまなざしは、抽象と具体の絶えざる往還が求められるだろう。
古野まほろは最初から会得していたその文体、徹底して制御された書きぶり、しばしば「芝居がかった」と評される語りによって抽象的な収容所の空間、演じられる舞台の空間をつくりあげることで、その具体的な事物を巧妙に回避する。もちろんそれだけなら寓話として読み得るところ、その抽象性へ過剰なまでに突き進むことで、もはや抽象的な論理だけが支配するような場をものしてしまう。もはや人間の身体さえ掻き消された空っぽの舞台のなかに言葉だけが響いて、幾何学模様の波紋をつくっている。――古野まほろの云う「本格ミステリ」とは、その正義とは、これである。
たとえば終盤において、犯人探しのためにつかわれる篩はいずれも、具体的な証拠の検討を欠いている。名探偵は拳銃の指紋を分析するのではなく、指紋があるかどうかさえ関係ないかたちで、指紋をめぐる犯人の行動を検討する。そこにはもはや論理しかない。指紋を調べるための道具はないし、彼女たちはそれを調べようともしない。映像記録も同様。犯行の可否も同様。虫眼鏡や顕微鏡を持ち出すホームズはいないのだ。これらは設定上の制約に過ぎないだろうか? 事件の性質から導き出された苦しい必然だろうか? けれども残された手がかりから過去を再構成するような歴史家的手続きとは正反対に見えるこの態度が、フィジカルな支配に抗するものとしてミステリを差し出す本書にあっては実に象徴的だ。そして本書に限らず、古野まほろのミステリのスタイルは、水も漏らさぬ精緻な論理と云うよりも、ただ論理だけがある、そんな抽象空間ではないだろうか?
もちろんぼくもまた、そんな論理が嫌いではない。むしろ、惹かれる。それを純粋論理空間ともてはやすことも可能だろう。けれどもそれによって何が取りこぼされるのか、いったい誰が検討しているのだろうか? ましてや、その正義を謳う本書において?
あるいは焚書についても同じように、物理的側面の排除が見て取れる。本書において書物は、徹底して名前だけの小道具だ。燃やされるための象徴だ。本書においては人間が書物に記録されるのではなく――ここでもまた、ホームズ譚を否定するかのようだ――書物が人間によって記憶される。過去を受け継いで語るのは人間であり、書物ではないのだ。
どうも、本書においては痕跡と云うもの――人間が過去を手繰るに当たってかならず手がかりとするもの――が信用されていないどころか、痕跡と云うものは無いも同然であるらしい。冒頭で引用した「たとえ私達が、この世界のインクの染みだって。」と云う台詞は、少女たちを書物のなかのインクの染みとして分解することを意味しない。むしろ本書は、インクの染みにすぎない記号を少女に擬したうえで、書物を消失させてしまう小説ではないか。演技の演技の演技の……、と云う特殊な入れ子構造は、そんな抽象性に拍車をかける。あるいはこう云っても良い。ここには人間しかいない。ホモ・サピエンスとかではない、抽象的な人間だけが……。
おそらくここに、ぼくと古野まほろの、いまのところ決定的に相容れないであろう違いがある。ぼくは徹底した弾圧をすり抜けるのは人間の強い意志ではなく、そんな支配をぎりぎりですり抜ける自然のちから、残された痕跡であると思う。そして知的な営為とは、そんな痕跡を分析して読み取ることではないだろうか? どんな事物もゼロから生まれることはなく、それはまた、ゼロに還ることはない。絶えざるつづく連鎖を跡づけることにこそ、連鎖を断ち切ろうとする暴力に抗する契機を、ぼくは見出す。
本書が謳い上げる探偵小説の正義は、なるほど対等と信頼を希求する点において、尊い。けれどもぼくにはその徹底が、一切を抽象の彼方へ突き抜けてしまうニヒリズムと表裏一体に思われてならない。
探偵小説は読者に参加の夢を与えると称しながら、実際は読者を操作するにすぎませんでした。[…]しかし、それでは、探偵小説はファシズムの隣に席を占めることにはならないでしょうか。
――天城一「『密室犯罪学教程』献詞」*1
そしてぼくは何より、本書が取りこぼす、と云うか、ないことにしてしまっているものが、「愛」とか「正義」の名の下に覆い隠されることを、おそろしいと感じる。思うに、探偵小説が見つめるべきは、その正義ではなく、悪ではないだろうか?
もちろんこれは、信念の問題だ。もはや作品の巧拙から逸脱している。けれども本書が作者の信条表明であるならば、それに応答しておきたいと思う。願わくは、みなさんの応答も聴いてみたいところだ。